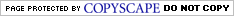犬は唸り声の違いをわかっている?
犬達は本当に唸り方の区別がついているのかを調べた実験があります。実験は41の異なった犬種を使い、犬達が唸り声の違いを理解するかをみるというもの。まず研究者は次の3つの状況での唸り声サンプルを20匹の成犬から録音します。①引っ張りっこをしている時(遊びで使う唸り声)②知らない人が近づいてきた時(見知らぬ者に警戒している唸り声)③他の犬が食べ物に近づいた時(食べ物をガードしている唸り声)次に骨付き肉を置き、一匹づつ犬が骨付き肉に近づける状況を作ります。そして犬の鼻先が骨付き肉に近づいた時に3つの異なったシーンで録音した唸り声のどれかを流し、犬の反応を見るというもの。実験を行う部屋の中には、飼い主と犬とのペアのみが入り他の犬はいない(録音テープを流すだけの)状況です。結果
・①引っ張りっこの唸り声では12匹中4匹がホネから離れた・②警戒の唸り声では12匹中2匹がホネから離れた・③食べ物をガードする唸り声では12匹中11匹がホネから離れたまた唸り声を聞いた後、二度とホネに近づかなかった犬は①、②ではそれぞれ1匹だったのに対し③では7匹もいたそうです。この結果をみると、人ではなかなか区別がつきにくい唸り声でもやはり犬達は違いを理解していると考えられます。唸り方で意味が違う
この3つのタイプの唸り声はそれぞれ違った長さ、ピッチやフォルマント(共鳴周波数)を持っているそうです。遊びの時の唸り声は他の2つに比べ短く、ピッチも高め。しかし食べ物をガードする唸り声と知らない人を警戒している唸り声の違いは、プロでさえもわかり難いそうです。しかし実験から犬達はわかり難い声の違いでも理解しているということがわかります。犬同士で学び合う言葉の存在
犬は人と暮らす中で人間とのルールを覚えますが、私たちが区別できない犬同士の言葉も身に付ける必要があります。母犬や兄弟犬と大切な幼少期を過ごし犬のルール、言葉を学ぶことは犬の健全な成長に欠かせないものだと言えそうです。